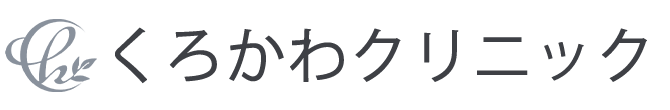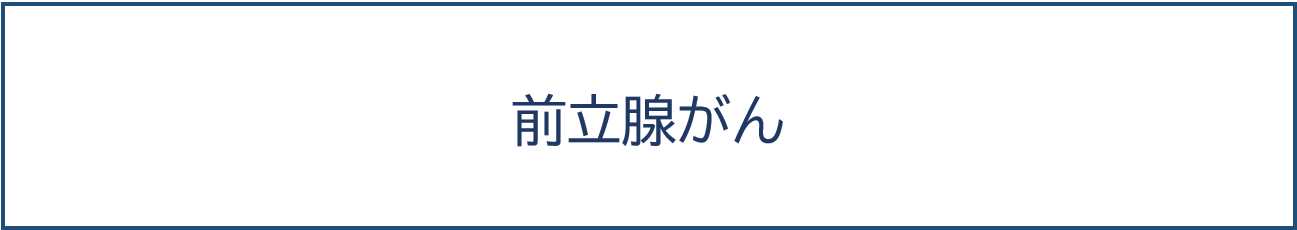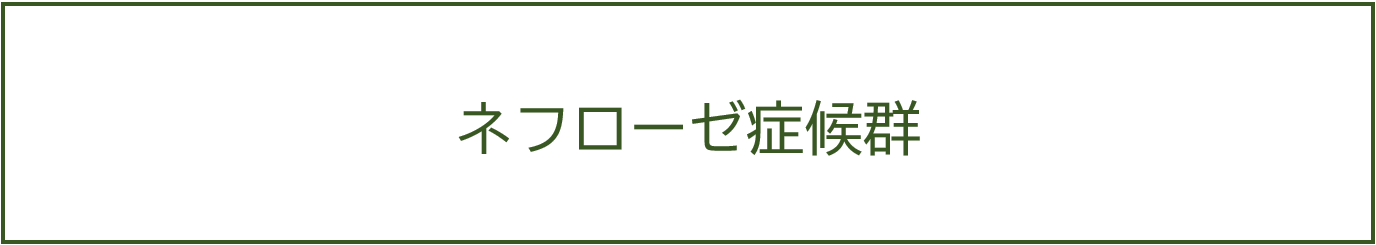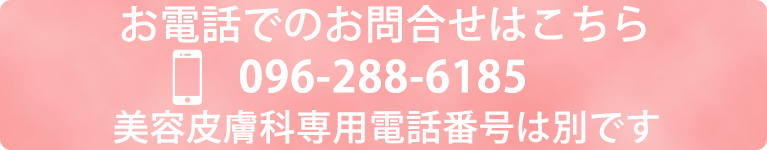泌尿器科
男性の疾患
前立腺肥大症
前立腺は年齢とともに肥大します。
その周辺には膀胱や尿道があるため、前立腺が肥大すると「尿が出にくくなる(排尿症状)」「尿がためられなくなる(蓄尿症状)」「尿をし終わった後にみられる症状(排尿後症状)」
などの症状が出ることがあり、この病気が「前立腺肥大症」です。
前立腺肥大症は進行する病気で、はじめは軽い症状ですが、進行するにしたがって症状が強くなる傾向があります。
症状が重くなるとトイレが気になって外出しにくくなり、趣味やスポーツも楽しめなくなってしまいます。
また、残尿によって結石や尿路感染症、腎臓病などの発症リスクも上昇します。
前立腺は30歳代後半になると肥大しはじめ、60歳では半数以上に肥大がみられます。
85歳までにはほとんどの男性の前立腺が肥大しており、その4人に1人に前立腺肥大症の症状が出ると言われます。
医療機関を受診する患者さんは年々増えており、男性ホルモンの関係や食生活の欧米化が原因としてあげられています。
患者さんの中には、年のせいだから治らないと誤解して諦めていたり、恥ずかしいという理由で受診しない方が大勢いるようです。
重症化すると・・・
尿道が閉じてしまい、尿が出なくなる場合(尿閉)や、自分で排尿できなくなり、残尿が増えると尿が絶えず少しずつもれることもあります(溢流性尿失禁)。
症状が軽いうちに泌尿器科を受診して、しっかり治しましょう。
前立腺炎
細菌感染により急激に症状が出現する「急性細菌性前立腺炎」、同じく細菌感染が原因で徐々に症状が発生し繰り返し起こる「慢性細菌性前立腺炎」に分けられ、多くは後者です。
前立腺肥大症の合併が多く、再発しやすいため、クリニックを受診してしっかり治すことが大切です。
主な症状は、発熱、排尿痛、排尿困難、頻尿などで、急性細菌性前立腺炎は38℃以上の高熱が出ることもあるなど強い症状を起こすことがあり、
慢性前立腺炎では急性前立腺炎が慢性化して発症するケースもありますが、ストレスなどによって発症することもあります。
前立腺疾患のほとんどは中高年の発症が多いですが、慢性前立腺炎は20~40歳代と比較的若い世代の発症が多い傾向があります。
全身症状は現われませんが、排尿・蓄尿症状をはじめ、排尿後の不快感や陰部の痛み、射精痛など症状は多様です。
前立腺がん
前立腺がんは、前立腺に悪性の腫瘍ができる病気で、前立腺肥大症とは病気が発生する部分が異なります。
自覚症状は初期には現われず、病気が進むにつれて、尿が出にくい、トイレが近い、尿が残った感じがする、など前立腺肥大症に似た症状や血尿、腰痛などが現われます。
30歳代にでき始め、症状や検査値の異常がないままゆっくりと進行し、50歳代ごろからPSA値の異常などがきっかけとなり、見つかることが多いです。
なので、早期発見には腫瘍マーカーのPSA検査が有効です。
健康診断や人間ドックのメニューにPSA検査が加えられるケースが増えてきていますので、50歳を超えたら定期的に検査を受け、早期発見・早期治療開始に努めることが重要です。
過活動膀胱
膀胱に尿がそれほどたまっていないにもかかわらず、勝手に膀胱が尿を出そうと活発に活動してしまう病気です。
トイレが近い、急にガマンできないほどの強い尿意を感じる、急に尿意をもよおして間に合わずにもらしてしまう、といった症状が現われます。
原因は、生活習慣に関する病気(高血圧や糖尿病)など様々ですが、男性の場合は、前立腺肥大症で尿道が狭くなることも原因になります。
尿管結石症
尿中にはシュウ酸カルシウムや尿酸など結晶化しやすい成分が含まれています。こうした成分が固まったものが尿路結石です。
尿路結石症は結石のできる場所によって、腎結石、尿管結石、膀胱結石に分けられます。
薬物療法で痛みを緩和させながら自然に排出されるのを待つ治療が一般的ですが、結石が大きい場合や結石が下降しない場合には結石を砕く治療を行います。
結石は再発しやすいため、治療後もこまめに水分補給を心がけ、定期的な検査を受けるようにしてください。
血尿
血尿は見た目でわかる肉眼的血尿と、見た目ではわからず尿潜血検査ではじめてわかる顕微鏡的血尿があります。
見た目でわかる血尿で痛みがある場合は膀胱炎や尿路結石症など、痛みがない場合には膀胱がんや腎臓がんや前立腺がんなどの悪性腫瘍の可能性があります。
また、尿潜血陽性の場合は、尿路の炎症や結石、尿路悪性腫瘍などが疑われます。
尿に血液が混じっている、尿の色が濃い、健康診断などで尿潜血を指摘されたといったことがありましたら、早めに泌尿器科を受診してください。
男性更年期障害(LOH症候群)
男性更年期障害とは、男性ホルモンの分泌が低下することで心や体に影響を及ぼした状態です。
40代後半から50代前半で発症することが多く、症状には、疲れやすさ、女性に対する興味の低下、イライラ、不安、疲労感、睡眠障害、勃起障害、性欲減退などが挙げられます。
男性更年期障害は、「男性ホルモンの分泌は緩やかに減少する」という特徴から、長くゆっくり進んでいくとされています。
診断確定は、医療機関で基本的な問診を行い、男性ホルモンの値を測定すれば比較的簡単に可能です。
男性更年期障害の治療法として、男性ホルモンの分泌促進を図る、生活習慣を改善するなどがあります。
女性の疾患
膀胱炎
主な症状には頻尿、残尿感、排尿痛、尿の白濁、血尿などがあります。
大腸菌などの感染によって炎症を起こしているので、適切な抗生物質の投与により数日で症状は改善しますが、しっかり治さないと再発しやすい傾向があります。
女性は男性に比べて尿道が短く、さらに外尿道口と肛門が近いので膀胱炎になりやすい傾向があり、特に20~30歳代の若い女性に発症が多くなっています。
トイレの我慢、疲労・睡眠不足などのストレスによる免疫力低下が発症の主な原因とされていますが、性交渉やシャワートイレなども感染リスクになることがあります。
膀胱炎は再発しやすいため、放置していると腎盂腎炎など深刻な病気につながる可能性もあります。頻尿、排尿痛、血尿などの症状が現れたら、できるだけ早く泌尿器科を受診してください。
腹圧性尿失禁
腹圧性尿失禁とは、くしゃみや咳、笑った時、ジャンプや重いものを持つなどの動作で腹圧がかかった時に、尿漏れを起こします。妊娠・出産、加齢などが原因で骨盤底筋がゆるむことで発症します。
女性は尿道が短いので特に腹圧性尿失禁を起こしやすい傾向があります。さらに肥満があると骨盤底筋にかかる負担が大きくなって発症リスクが上がります。
過活動膀胱
排尿筋が過剰に収縮してしまい、膀胱に尿を溜めておけずに、頻尿や突然の強い尿意などの症状が現れます。
原因によって神経因性とそれ以外の非神経因性に分けられ、8割以上が非神経因性とされています。
神経因性過活動膀胱は脳と膀胱を結ぶ神経の障害から起こっていますが、非神経因性過活動膀胱は骨盤底筋の衰え、下部尿路の閉塞、女性ホルモンの減少による膀胱の過敏化などが主な原因です。
頻尿、睡眠中何度かトイレに起きる、尿意切迫感(突然の強い尿意)、切迫性尿失禁(突然の強い尿意でトイレに間に合わない)などがあります。
尿に関するお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
尿路結石症
尿中にはシュウ酸カルシウムや尿酸など結晶化しやすい成分が含まれています。こうした成分が固まったものが尿路結石です。
尿路結石は発症した場所によって腎結石、尿管結石、膀胱結石に分けられます。
結石は腎臓で作られますがその時点では症状を起こすことがほとんどなく、細い尿管に落ちてくると突然激しい痛みなどの症状を起こします。
結石が尿路の粘膜を傷付けて炎症を起こし、詰まって尿の流れが滞るため、背中・わき腹・腰の激しい痛み、発熱、血尿などを起こします。サイズが小さければ自然に排出されて症状が治まることもありますが、結石が大きい場合には結石を砕く治療が必要になることがあります。
中年以降の男性に発症しやすい傾向がありましたが、近年は女性や若い男性の発症が増えてきています。結石は再発しやすく、腎機能低下につながる可能性が高いので、早期発見と治療がとても重要です。
腎臓内科
慢性腎臓病
慢性腎臓病は、腎臓の働きが低下した状態や、尿の中にたんぱくが漏れ出る状態(たんぱく尿)の総称で、様々な原因によって腎臓の働きが徐々に低下していく状態のことを言います。
慢性腎臓病は腎臓の働きがかなり低下するまで自覚症状がありません。そのため気づきにくく、油断しがちな病気といえます。
主な症状はだるさ、食欲不振、頭痛、吐き気、むくみ・動悸・息切れ、高血圧、貧血、骨が弱くなるなどです。
いろいろな症状が現れるのは、腎臓の働きが低下することで体内にさまざまな有害物質がたまってしまうためです。体内に余分な水分もたまるので、むくみが生じ、血圧も高くなります。
慢性腎臓病は、「脳卒中」や「心筋梗塞」などの原因になることも明らかになっています。最後まで進行すると腎臓が機能しなくなり、透析治療など、自分の腎臓の働きの代わりをする治療を行わなければなりません。
その前に定期的な検査で早期発見をすることが重要です。
特にこんな人は要注意
●尿検査で尿たんぱくが出ている
●尿の色が濃かったり、泡立つ
●夜に何度もトイレに行く
●息切れしやすい
●顔色が悪いと言われる
●ひどいむくみがある
●貧血や立ちくらみがある
●疲れやすく、常に身体がだるい
生活習慣の乱れなどによって腎臓への負担が大きくなると、慢性腎臓病を発症する危険性が高まります。
低下した腎機能が回復することは基本的に期待できず、進行予防のためには糖尿病、高血圧、高尿酸血症など生活習慣病の治療や食事管理、適度な運動、禁煙といった生活習慣の改善が大切です。
腎盂腎炎
腎盂腎炎とは、腎盂・腎杯さらに腎実質が細菌性によって炎症を起こしている状態で、細菌が膀胱から尿の流れとは逆行性に侵入することによって生じる感染症です。
急激に発症し、臨床症状や炎症所見が強いものを急性腎盂腎炎、比較的症状が軽く微熱や食欲不振などが主症状であるため経過が長く続くものを慢性腎盂腎炎と呼びます。
血液中に細菌が侵入する菌血症・敗血症に進行しやすく、早急に治療する必要があります。
主な症状は、発熱・悪寒・腰の痛み・だるさ・吐き気などです。
慢性腎盂腎炎は目立った症状がないことも多く、一般的に自覚症状が少ないことが特徴です。長引く食欲不振や倦怠感があり、徐々に腎臓の機能が低下することで尿を濃縮する能力が低下し、夜間の多尿や尿の色が薄くなるなどの症状が現れます。自覚症状が少ないため気付かれないことも多く、治療せずにいると慢性腎不全に移行することがあります。
ネフローゼ症候群
ネフローゼ症候群は、腎臓に障害が起こり、本来漏れでない量のタンパク質が尿の中に漏れ出る状態です。その結果、血液の中のタンパク質が減少し、様々な症状が現れます。主な症状には、全身のむくみ、体重増加、蛋白尿、高血圧、貧血、肺水腫などがあります。
ネフローゼ症候群は、一次性と二次性の2つに分けられます。一次性ネフローゼ症候群は、明らかな原因疾患がない腎臓の糸球体に起こる病気が原因です。
二次性ネフローゼ症候群は、糖尿病などの全身に影響する病気や薬剤が原因です。